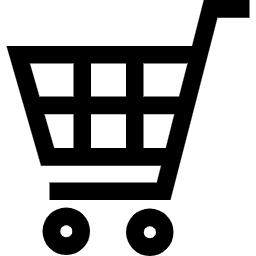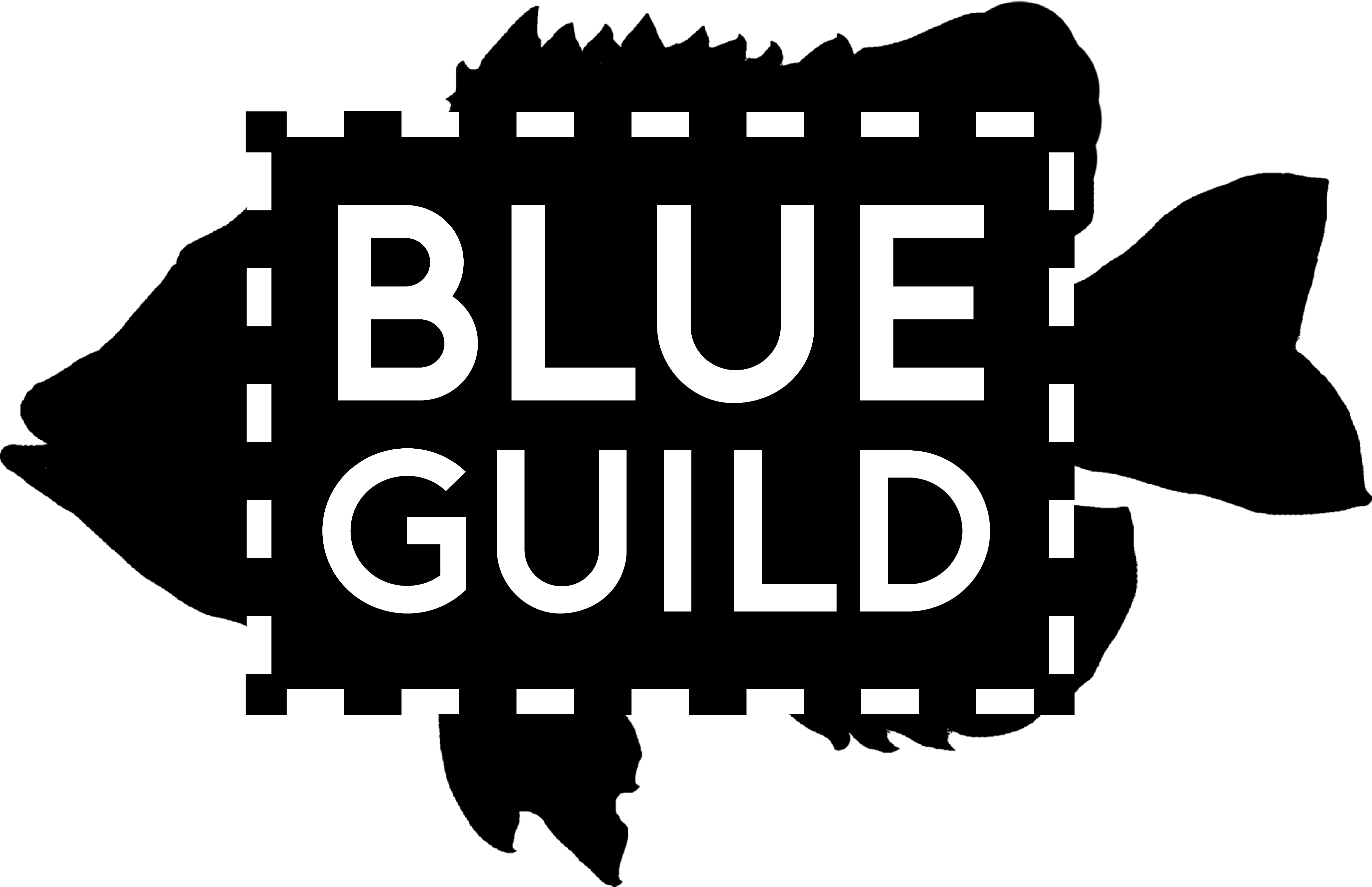
目を覚ます。嫌な気分になりながら、目を覚ました。
寝汗が、べっとりと身体に、まとわりついている。目覚めて、最初に入った視界を邪魔する前髪は、顔を振ってもはらわれねぇ。汗でくっついて、はらわれねぇ。
「あー、うぜぇ。切ろうかな」
枕元の時計を確認すると、まだ深夜の四時をまわったところで、勿体ない気持ちになりながら、身体を起こす。どうせもう眠れねぇんだよな、こうなると。
「くそ、もったいねぇなぁ」
出社目前に眠くなるのはもうお決まりみたいなモンだから、とりあえずコーヒー淹れよ。カフェインに頼るくらいしか、選択肢無ぇ。
選択肢、という言葉を頭に浮かべたら、洗濯をしたくなった。そろそろ着られる下着が無ぇ。あったっけ?まぁ洗濯すりゃいいんだ。
いっそのことパジャマも洗おう、と思って家の中で真っ裸になり、下着をネットにしまい込んで、ポイっと洗濯機の中に放り込む。
高かったけど、ドラム式洗濯乾燥機を買った自分を褒めたい。一番高い買い物だった。人生で。マジで。あ、嘘。車の方が高ぇわ。でも車って一括じゃねぇからな。
なにより、汗だくになりながら洗濯物を干す、という行為が嫌い。大嫌い。というか、汗をかくというのが世界で一番嫌いで、二番目に嫌いなのはゴキブリ。三番目に嫌いなのは大きな音を立てて飛ぶ虫。セミとか。
だから、あたしは総じて、夏が嫌いなんだわ。
☆
「あ~~……うっぜー」
「フウ、夏嫌いだもんね」
「大っ嫌い、な。あたしに何もしてくれない。不快感しか与えてくれない」
「夏生まれなのに?」
「ユキだって冬生まれなのに冬嫌いじゃん」
「でも雪は好きだよ」
「腐るほど降るから?」
「なんかいいじゃん。静かになる感じとか。あと名前の由来だし」
ユキはそう言うと、立ち上がり、教室の隅へ歩き出した。冷房をつけてくれる。
「いいの?勝手につけると先生に怒られっぞ?」
「フウってギャルのくせしてビビりだよね」
「ギャルはみんなビビりなんだよ。だから派手にすんだろ」
冷房をつけたユキは、カーディガンを羽織る。
「寒がりなんだから無理しなくていいんだぞ」
「フウってギャルのくせして優しいよね」
「ギャルはみんな優しいんだよ。だから今日学校居んだろ」
「そうだったね。そして私は、目撃者というか、証人?」
「悪ぃことしたみたいに言うの、やめてくれませんかね。というか助けようって言ったのユキでしょ」
夏祭りで、迷子の子供を保護して、交番まで届けた。ただそれだけで、学校から呼び出され、このクソ暑い真夏の、夏休みのケツに、わざわざ『始業式での表彰の練習』とかいう、クソの積み重ねのようなイベントをする。
金髪にして、化粧して、ネイルして、口が悪く、目つきが悪い。それだけで日常から悪い意味で目をつけられているギャルが、人助けをしたというだけで、ここまで騒ぐ。東大でも入ったら全員腰抜かすんじゃねぇかな。
一方、ユキは、髪は黒くて、バレない程度の化粧をして、爪は地で、言葉遣いが大変よろしくて、目元は垂れている。それなのに、あたしの友達で、この間の夏祭りも、ユキからの誘いが無ければ行っていない。それにこいつは多分東大に入る。周りもそれを不思議とは思わないだろうね。
不公平だなんて思わない。そこまでガキじゃない。
他愛のないことを話していたら、先生が入ってきて、「お前が先に表彰状を受け取れ」と言われ、その通りに練習して、本番の始業式も問題なく終わって、それは大嫌いな夏の終わりを示していて、あたしの心は踊りはじめたってワケ。
☆
仕事を終えて、家に帰ってくる途中、風が涼しさを携えていて私は思い出す。高校の頃の友人を思い出す。
彼女は、普段悪ぶっていたけれど、根は優しくて、そして夏が嫌いな女の子だった。高校を卒業してから、少しは連絡を取り続けていたけれど、徐々に疎遠になって、今は何をしているのかは分からない。
彼女が夏を嫌悪する気持ちと同じくらい、私は冬を嫌悪していた。吹きすさぶ風も嫌だったし、割れる唇も嫌だったし、重ね着をしても寒い屋外と、暑すぎる屋内のギャップが嫌だったし、なにより今は、名前の由来になった雪を、東京人は求めていなくて、そして私は冬が更に嫌いになった。
交通機関が止まる、とか。滑って転ぶ、とか。タイヤを換えていなくて事故る、とか。降ったはいいけど少ないと嘆く子供、とか。
東京の人が、ここまで愚かな生き物だとは、弱い生き物だとは、思っていなかったから、連鎖して、私は東京も嫌いになった。
「実家、帰っちゃおうかなぁ……」
同棲していた元カレが浮気をしていて、私がそのことに対してヒステリックに叫んで、出て行って、そして居なくなった。東京に来て最初に付き合った人にも、二人目にも、三人目にも、浮気されて、同じように別れた。
三人とも、冬に別れた。
広すぎる部屋に、私の言葉は溶けて消えた気がした。
☆
「ユキさん。俺、ユキさんのこと好きなんです」
研究室の後輩である、ハセガワ君はいきなり、二人っきりの研究室で、背中合わせに座っている私に、そう言った。
「そ、そうなんだ」
突然言われても、反応に困る。そして沈黙が流れた。
確かに、一緒に遊びに行ったりしていたけれど、急すぎない?
長すぎる沈黙に耐えかねて、ハセガワ君は立ち上がり、私の横に来た。
見上げると、目が合い、向こうが即座に逸らした。
その姿を、かつて助けた迷子の男の子に重ねてしまって、私は噴き出した。
噴き出した私を見て、彼はムッとする。
「いやぁ、ごめんごめん。笑ったのはごめん。ちょっと思い出し笑いしちゃって。うん。いいよ。というか、こちらこそよろしく」
私はそれだけ言って、目の前のパソコンに向きなおした。
「え、それだけですか?」
「それだけ、って?」
「あ、いや。なんか、こう」
「しっくりこない?」
「いや、そういうワケではないんですけど」
パソコンから目を離して彼を見ると、頭の後ろ側をポリポリと搔きながら、どんな表情をするのか悩んでいる顔をしている。
「じゃあ」
それだけ言って、私は立ち上がり、彼の唇にキスをした。
瞬間だけで、すっと身体を引いて、椅子に座りなおして、またしてもパソコンに向かう。
彼は、立ったまま硬直して、私の研究を邪魔しない置物になった。
その後、二つの秋と、一つずつの冬、春、夏を共に過ごして、彼とは別れることになる。
☆
久しぶりに地元の駅に降りた。日本海側にある、日本最大級の穀倉地帯。コシヒカリの田園調布と言ったところだろうか。まぁ、要は新潟県だ。
駅前は大きく変わっていた。特に駅南と呼ばれる駅の南側は進化と呼んでいいほどの発展を遂げている。
久々にこの土地で、輝く黄金のパッチワークを眺めたら、東京嫌いの裏として、新潟が好きになるかもしれない。昔は何も無い、と決めつけていたけれど、東京にだって何も無かった。何かあるような顔をして、何も無い。求めない者には何も与えない街。
完全な黄金色の季節。新幹線の中から見えた、私が求める景色。彼女の髪色のような美しい黄金色。
☆
洗剤が無かった。腹立たしいから会社休もう。やってらんねぇってやつ。まだ暑いし、今日会社行ったってどうせ途中で眠くなるし。期末?それがどうした。夏が終わるんだから九月はあたしにとっちゃ年始みたいなモンだ。
冷房の温度を20度にして、真っ裸に毛布を被り眠った。
ちょっとして起きて、流石に凍え死ぬかと思って、ベッドを降りたらなんかを踏んだ。
洗濯して、仕舞っていなかった服だった。服といっても、ジャージだけど。ただ、まぁ無いよりはいいので、それを着る。下着は何もつけていない。だって一回脱いだ下着ってもう一回履きたくないじゃん。その心理。
駅のドラッグストアで洗剤買うべ。
そう思ったのを後悔するくらいには、まだ暑かった。そりゃ真夏よりはマシだけどさぁ。どうにかなんないモンかね。駄目だ、駅行く前にアイス買おう。
棒アイスを買って、エスカレーターを上っていたら、見覚えのある後ろ姿があった。誰だ?
アイスをかじりながらふらふらと歩いていって、ちらっと横目で横顔を確認する。
☆
「お、ユキじゃん」
「え?」
突然、名前を呼ばれて振り返る。振り返っている途中で、頭がこう囁く。この声を、知っている。そして、懐かしい気持ちがする。そう、囁く。
「……フウ?」
アイスをかじりながら、ダサいジャージを、何故か暑いのが嫌いな癖に一番上までジッパーを上げて着ていて、それなのに腕と脚は巻くっている。変わらない、あの黄金色が、黒いジャージに映えていて、私は思わず頬が緩む。
「どーしたん?これからユキの大っ嫌いな冬が来んのに。里帰り?」
目つきの悪さは、変わっていない。そして私が冬嫌いであることも、覚えていてくれていた。
久しぶりなのに、そんな気配は一切匂わず、まるで昨日まで一緒にいたかのような、『当たり前』。
「まぁ、そんなとこかな」
「元気?」
「まぁ、ある程度は?」
「聞き返されても知りませんけどね。今年クソ暑かったから死ぬほど雪降るんじゃね?」
「まぁ、それも見たくて帰って来たみたいなところ」
「ふーん。じゃあしばらくこっち?」
「ていうか、こっちに戻ってくる」
「ほーん。ならまた遊べんじゃん」
「ふふふ、そうだね」
「あ、じゃあ薬局付き合って。洗剤買うんだわ」
アイスを食べ終えた彼女は、私にそう言うと歩き出した。
「うん、いいよ」
私もそう返事して、隣を歩く。
「ていうか思ったより暑いね、フウ我慢できないんじゃない?」
「ほんとだよなぁ、嫌んなる」
「それなのになんで一番上までジッパー上げてんの?」
「ノーブラ・オン・ジャージだからな」
「ジャージの上は普通ノーブラだよ……」
「ごちゃごちゃうるせぇなぁ」
怒ったようにニヤニヤと笑う彼女を見る。
美しく透けるような、白金に近い、揺れる髪が目に映る。
そして私は思う。
この黄金色が、ずっと横にいれば、私に冬は来ない、と。