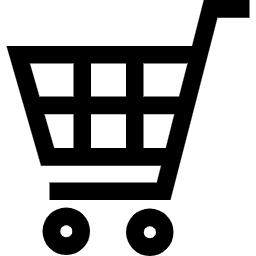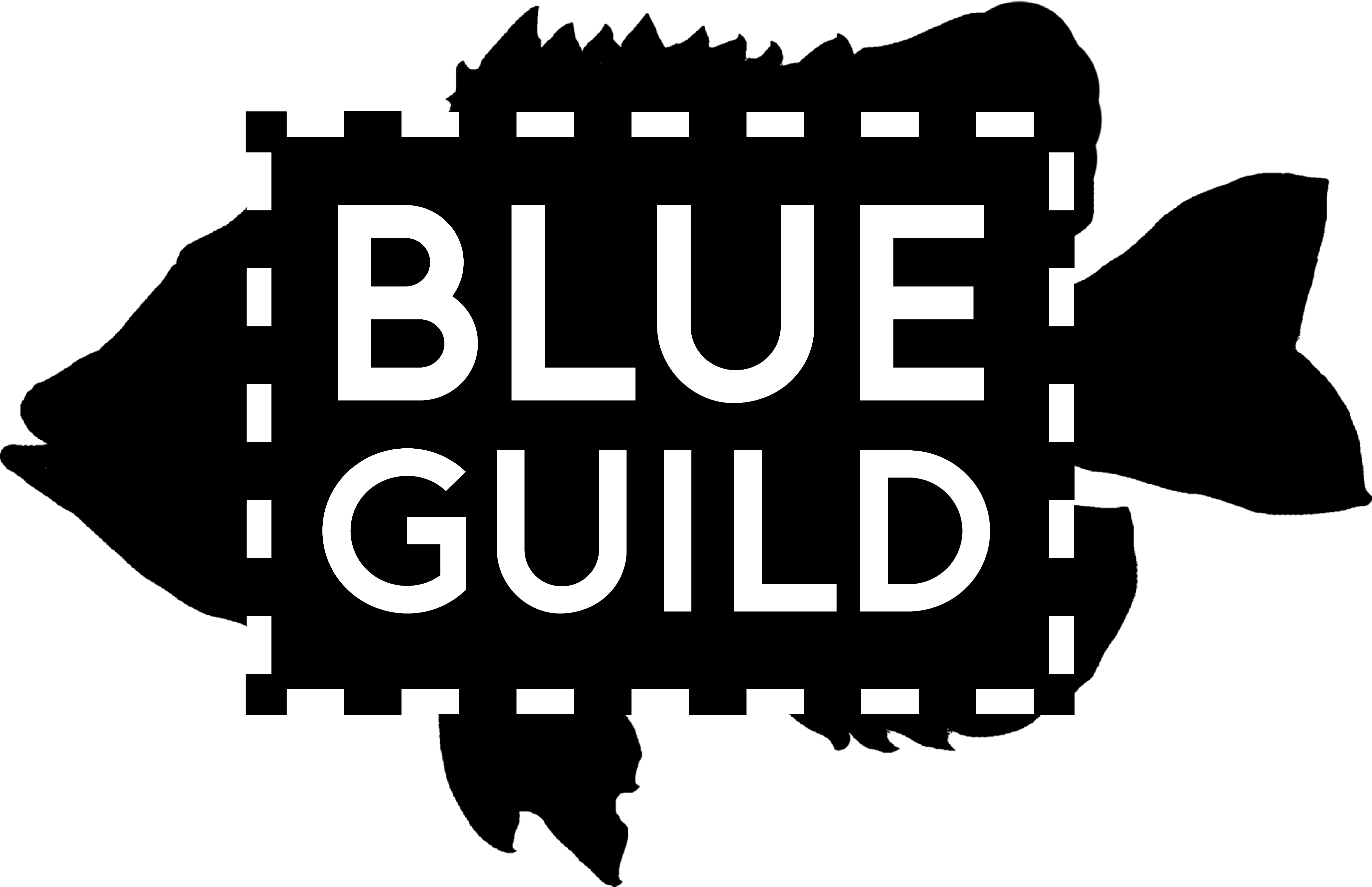
「ねぇ、肝試し行かない?」
隣の席から、小声でユミが声を掛けてきた。秋の訪れを伝えるような、心地よい日差しを窓から浴びて、うとうとしていた私は、思わず授業が終わったのかと勘違いしてしまう。
前を向くと、現国のハヤシが黒板に何やら書いていた。
良かった。まだ授業中だった。何が良かったのかは分からない。
「いいけど、誰と?」
「光小のメンツ。アヤコとアキコの双子も来る。男はカツとミノルと、あと誰だっけ」
「私に聞かれても」
「まぁとにかく女四人と男三人って感じ」
「ふぅん」
正直、興味は無い。無いけれど、部活も引退して暇だったし、夏期講習にはうんざりしていた。
「いいよ。いつ?」
「今週末の日曜。夏祭りのあと」
「うわー、懐かしい。まだあの祭やってんだ」
「そうよ。みんなでお祭りうろうろして、その後肝試しってワケ」
と、いうわけで、週末になった。
せっかくのお祭りなんだから!というユミの発案で、私たちは浴衣を着ることにした。
「肝試しするなら動きやすい方がいいんじゃない?」と提案しても、「せっかくのお祭りなんだから!」としか答えない機械と化したユミを止められる私でもなく、彼女の言い分に従う。
ユミは実に女の子らしいピンクを基調とした浴衣で、私は我ながら地味だとは思うけれど気に入っている、臙脂色を暗くしたような色の浴衣を着る。
ユミは小学校からの付き合いで、受験先がことごとく被り、高三になった今も同じクラスという腐れ縁だった。
「こっち側来るの久々~」
「まぁ、駅は綺麗に反対側だからね。こういう機会無いとなかなかこっち側来ないわ」
夕暮れにさしかかり、道歩く人々も夏の終わりの気配に浮足立ちながら歩いている。
家族連れ、カップル、そして私たちのような友達同士。みんなそれぞれ、まだ暑さの残る夕暮れを歩いている。
坂を下った先には光が灯されていて、遠くからでもお祭りの熱気がここまで漂ってくる。
「「久しぶり~」」
集合場所である鳥居脇に着いたら、双子のアヤコとアキコが居た。二人は柄は同じだけれど色の違う浴衣をそれぞれ着ていて安心する。
これで見分けがつく。
「赤い方がアヤコ? それともアキコ?」
「「どっちでしょ~」」
声を揃えて言う二人に多少うんざりした気持ちを抱きながら、無視する。
少し遅れて男子たちも来た。カツは野球部だったので、引退してもまだ髪は短いままで、ミノルは見事にチャラい風貌をしていた。小学生時代を知ってしまっているからこそ、笑えてしまうけれど、彼なりの高校最後の悪あがきなのだろう。
「わり、遅れた。あとハネスケは肝試しから合流だって。祭で家族の手伝いしてるらしい」
正直、ぎょっとしてしまった。ハネスケ来るのか。
ハネスケは、羽田太輔。頭と後ろをとって、あだ名がハネスケ。
小学校の卒業式に、告白されて、振った男だった。
ユミがこちらを見てニヤニヤしている。
だからあのとき忘れたフリをしたのか、と思うけれど、別に恨みはしない。
それに卒業から丸五年ちょっと経っているのだし、それから一切連絡を取っていなかったのだ、
もう私のことなんて忘れているだろう。
「まずは、一通り全部見てからにしよ」とユミが提案すると、「いいじゃねぇか、めんどくさい。いまバイトしてて金入ってるし好きなとこで好きなモン食いまくろうぜ。どうせ並んでる屋台なんて定期的に同じのがあるだろ」とカツが却下して、「「ミノルって今どこ通ってんだっけ~?」」と双子が話の流れを無視して話しかけると、「〇〇大の附属、大学受験無くてラッキーっしょ」とミノルはドヤ顔で答える。
そんな様子を見ていると、意識が過去にタイムスリップする。
休み時間、ボールの片付けを押し付け合う男子。昨日見たドラマの主演に恋して語り合う女子。体育での手つなぎ鬼で、女子よりも実はドキドキしていた男子。そうと知ってしまうと、どこか恥ずかしくなる女子。給食の時間、最速のおかわりの為にいかに「いただきます」の前に量を減らすかという思考を張り巡らせていた男子。それを横目に、アホなことしてるねーと楽しくおしゃべりする女子。
昇降口や、たまに開放される屋上、校庭を走る、昔好きだった脚が速い人などなど。
場所も風景も人も音も、それらが一気に押し寄せてきて、まだじめっとした夕暮れ時から逃げるように意識が飛び回る。
すると、一人の男の子に辿り着いた。
その子を見たのは、小学生の頃に、今回みたいにみんなで来たお祭りで、同じ神社で、同じような場所だった。
鳥居の近くだったから覚えている。
確かにこの場所だ。
その子は美しいくらいに存在が朧気で、人の波をすいすいと避ける。ただ、どこかに歩き出すワケではなくて、私たち集団のことをずっと見ていた。
最初は、誰かの弟かなとも思った。ただ、誰もその子に話しかけない。前髪は長くて、目は隠れていて、そして身体は細い子供だった。灰色の甚平を着ていて、ずっと人をよけながらこちらを見ている彼に話掛けようとして……
「チヨ!」
ハッと意識が祭の中にいる自分に戻る。ユミが少し離れたところから私を呼んでいた。
「ほら、とりあえず一周しちゃお。はぐれちゃうよ」
なるほど。カツはなんだかんだ女の子の意思を尊重する奴だったな、なんてことを想いながら私は、じっとりとかいた手汗と、冷たく背中を流れる汗を無視するように、みんなの元に歩き出した。
そして、夕闇が夜闇へと完全に空の支配権を変化させて、私たちは少し離れたお寺のお墓に辿り着く。
完全に夜になったからか、少し風が冷たい。夜泣きの虫もまわりを取り囲むように参加していて、どこか孤立した場所に思える。
「あれ? ハネスケは?」
「あいつ、片付け抜け出せなかったらしいんだよな。それに、なんか自分のとこの屋台の前で、迷子っぽい子供見つけたらしくて、その対応もしてるっぽい」
「「ぽいぽい言ってる~」」
「うるせぇ」
「ハネスケは昔から優しい奴だったからな。ほっとけないんだろ」
「そうそう、優しかったよね」
そう言って、私を見るユミ。目元が三日月になる彼女の笑顔を私は知らん顔して続ける。
「そうだね」
「じゃあ早速」とカツがくじ引きを取り出した。
「男二人、女四人だから。まぁ三人ペアか」とミノル。
「「私たち離れたくな~い」」と甘ったるい声を出す双子を軽くあしらって「じゃあ、俺が一、ミノルが二だから」とくじを私たちの前に突き出す。
私とユミは、一を引いた。
はからずも、双子は一緒になりミノルと先に歩き出した。
今はチャラいけど、昔は極度のビビりだったミノル。めちゃくちゃマイペースな双子姉妹。このトリオの道中は確かに面白そうだった。
実際、双子がぐいぐいとミノルの腕を掴んで歩いていく。
残された私たちは、十分後のスタートになった。
「あれ以来、ハネスケと連絡とってねーの?」
カツが暇つぶしと言わんばかりに私にそう声を掛ける。
「ないよ。そもそもあのとき携帯とか無かったし」
「ハネスケの家、神社らへんだもんねぇ。わたしたちの家は駅側だから、本当に会わなかったよね」
ユミが助け舟を出してくれる。
「ふーん。で、今はお前ら彼氏とかいんの?」
ぷふふ、と突然笑い出すユミ。
「なんだよ、気持ちわりーな」
「お前らって、って思っちゃって。ふふ、ごめんごめん。ほら、カツって昔」
「チヨちゃん、ユミちゃんって呼んでたよね。ふふ」
私もつられて笑ってしまう。
「ばっ……」と頬を染めながら身体を乗り出すカツ。そんな凄まれても、私たちの中では「チヨちゃん、ユミちゃん」でインプットされてしまっているのだから、今更だ。
それにしても、と思う。高一の時にたまたま駅で会ったカツはまだ身体は薄っぺらかったのに、名門校で揉まれるとここまで分厚くなるのか。
「なんだよ、ジロジロ見て」
まだどこか恥ずかしそうなカツ。
「惜しかったね、甲子園。観てたよ、テレビでだけど」
そう言うと、カツは黙ってしまった。
少しの沈黙が流れて、「まぁ、後悔とかはあんまねーな」とやたらと晴れ晴れとした面持ちで前を向く。
女の子に対してなんだかんだ優しくて、ずっと坊主頭でやんちゃだったカツを好きだったことを思い出した。
ユミが。
本来なら一のチームはミノルと双子で、二のチームはカツとユミ、そして三のチームはハネスケと私だったのだろう。
いかさまにも近いくじ引きは、おそらくミノルとユミの合作で、最初からミノルはあの双子と行動を共にすることが決まっていたのだろう。
憶測にすぎないけれど、そんな考えが頭をよぎる。
「お、十分経った。行こうぜ」とカツが私に声をかける。
ユミとカツを前に歩かせて、少し離れたところで二人を見守ろうと思って、遅れて私は歩き出す。
少し歩くと、ふと墓石の隙間を誰かが走ったような気がした。
そして、お墓の隙間で立ち止まると、私をじっと見つめる。
闇に光るその子供は、見たことのある朧げな雰囲気をまとっていて、涼しいのに嫌にまとわりつく湿気と共に、立ち止まって私は思い出す。
小学生の頃のお祭りに、また意識を飛ばす。
その頃も、こうやって肝試しをした。
そしてあの頃も、今日みたいに涼しかった。
「あれ? あの子、さっき」と思って口に出した言葉をかき消すように、その男の子は右手の人差し指を口元にあてた。
私の意識はその子に集中して、そして身動きができなくなる。足元に根が張ってしまったかのようで、でもそれは何も恐怖心を煽るものではなかった。
どこか温かい、彼のまとわりついている美しく怒る朧気な空気が、私を包んだ。
それは温かくて暖かいのだけれど、嫌な湿気を含んでいなかった。
ついてこい、と言わんばかりに彼は歩き出して、そして私の足は吸い寄せられるように、根を失くした樹が倒れるように、彼に向かって歩き出した。
そこで……
「チヨ!」という大きな声が墓地内に響く。
前からカツとミノル、双子、ユミが順番にこちらに向かってきた。
そうだ。あの頃も、こうやって誰かの呼びかけで私は立ち止まった。改めてその子を見ようとしたけれど、姿は無くなっていた。
これもあの頃と同じ。
「ハネスケが、片付け中に突然いなくなって、それで……神社の井戸の横で倒れているのが見つかっ……」
そして私は眼を覚ます。横からユミが私の肩を叩いている。秋の訪れを伝えるような、心地よい日差しを窓から浴びて、うとうとしていた私は、思わず授業が終わったのかと勘違いしてしまう。
前を向くと、現国のハヤシが黒板に何やら書いていた。
良かった。まだ授業中だった。何が良かったのかは分からない。
隣からユミが囁く。ノートの切れ端に一、二、三と書いた複数のそれを見せながら。
「ねぇ、肝試し行かない?」