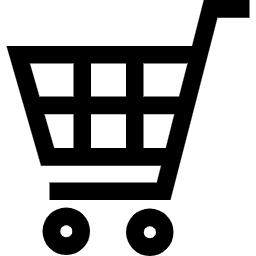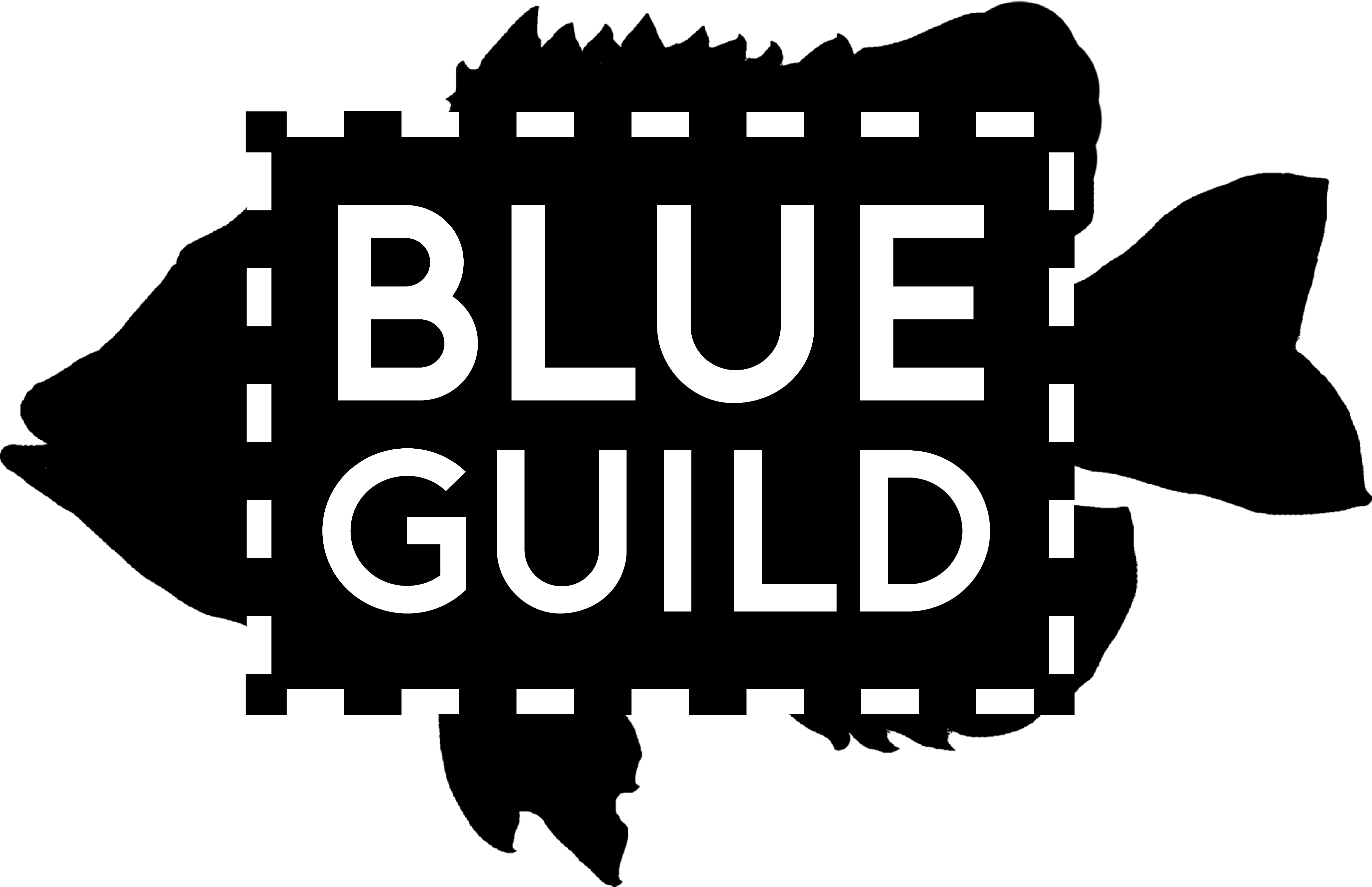
「好きな作曲家とか、影響を受けた音楽は何?って聞かれたときさ、なんて答える?」
また始まった。こいつは、飽きもせず何を言ってんだ。と、いう感情を悟られてはならない。ここできちんと答える、もしくはそのポーズを見せてやらないと、明は長めに拗ねることを卓也は経験からわかるようになっている。後々非常に面倒くさいのだ。
明のいつになく真剣な眼差しを、ctrl+C。丁度自分も同じことを考えていたよ、と言わんばかりに深い呼吸を鼻から鳴らす。そして卓也は眉間の皺を人差し指でなぞりつつ、ゆっくり俯く。目を細め、あたかも、こんなに奥の深い質問にゃ簡単に答えられんぜ、と言わんばかりだ。この間、卓也が鳴らした音は鼻息のみ。まだ一言も、発していない。
卓也の一連の行動は、ただの時間稼ぎだった。今回、卓也は「何かしら答える」ではなく「答えようとする風のポーズをとる」を選んでいた。
「俺はね、ドビュッシー。やっぱほら、逆にクラシックとか行っておいた方が、かっこいい感じ出そうじゃない?」
正解だった。明が勝手に喋りだしたところで、卓也は自分の選択を誇らしく思った。
明がしてくるこの手の質問は二つのパターンがある。一つ目は本気で答えを求めているとき。もう一つは、ただ明自身の考えを発表したいパターンだ。
今回は後者、というか明は基本後者だった。こいつは、普段からこんなことばかり考えてるんだろう、半ば卓也は呆れていたが、そんなことにも慣れていた。正直卓也は、「いつそんなこと聞かれるんだよ?」とか「逆にクラシックの”逆”ってなんだよ」だとか「何を想定してんだ」など、色々突っ込みを入れたかったが、自分が今読んでいる漫画からなるべく意識を切り離さないことの方が大事だった。
明はまだペラペラ持論を展開しているが、卓也にとってはもう今週のコマ割りの斬新さの方が興味深かった。
しばらく経つと静かになった。どうやら明も馬鹿ではないらしい、卓也が漫画に集中している、もとい彼の話に殊更興味を持っていないことに気づいたのだ。イヤホンを耳に嵌めている。明はこの時間はお笑いの動画をぼーっと眺める方向にと、舵を切っていた。
彼はお笑いがとても好きだ。まだテレビに出ていない芸人はもちろん、某漫才大会なんかは1回戦から追っている。ただ、お笑い芸人の漫才やコント等ネタ動画や、芸人がやっている番組を観ているときの明は少し怖かった。
先ほど卓也がやってみせたように、眉間に皺をよせ目を細めながら観る。そして、時々短く鼻を鳴らす。普段喋っているときは、下品で豪快に、文字起こしをすれば「あ゛っはっはっは」と表せるよう笑う明だが、動画を観ているときに限っては「フッ」と鼻で笑うのだ。卓也にはどちらが明の本当の笑い方かはわからなかったが、前者は不快で後者は不気味だった。
携帯に目を移すと、外の気温は32°だと示していた。
ただ、卓也は冷房の効いた部「フッ」屋で漫画を読んでいる。優雅にリラックスする夏貴族。心が穏やかだっ「フッ」た。クーラーの唸り、扇風機がが撫でる頬、「フッ」蝉の詩。「フッ」
『・・・うるせえな』
卓也はながら読みが出来ない。この場合の最適解は、音楽を聞きながら、漫画を読む行為。それが出来ない卓也の耳は今、自由だった。耳に染み入る鼻の声。夏の風情が台無しだった。
風情。卓也はこの煩わしさの責任を明にとらせるべく閃いたことを口にした。
「なあ明、花火とかしない?」
「フッ」
イヤホンをもぎ取る。
「んぁ、、なん?」
「だから、なんか夏っぽいことしない?」
「今、すげーしてんじゃん」
なるほど。確かにそうだ、と卓也は妙に納得していた。
面倒そうにイヤホンを嵌め直した明は、携帯を横に構えたまま、ごろんと寝ころぶ。卓也は今週分の小年誌をもう読み終えてしまったため、暇を持て余していた。まだ日曜の14時。週末の予定は特になかったが、時間はたっぷりあった。起きた時刻も昼過ぎだったため、たいして空腹は感じていない。とはいえ、手持ち無沙汰の卓也はじっと座ってるのももどかしくなり、近所のスーパーまで足を運ぶことにした。
「セイユ―行くけど、なんかいる?」
「・・・・・・・・・・・・・・フッ」
「あいよ」
家を出てすぐに後悔した。気温が高いのも嫌だったが、日差しが強く、肌が痛かった。
日が肌を刺すとはまさしくこういうことだなと、妙な納得感を覚えながら卓也は、お笑い一方向受信機に成り果てた明について考えた。
彼とルームシェアを始めて、もうそろそろ二年が経とうとしていた。卓也と明は大学時代からの友人で、知り合って十年目になる。
ルームシェアを始めたきっかけは、明からの誘いだ。
大学時代の別の友人とボードゲームを作ったり、音楽を作ったり試行錯誤しながら生きている卓也を羨ましく思ったらしい。それならばと、卓也たっての希望で戸建てに住むこととなった。場所は東京と埼玉の境。大雨が降ると街中の電気が止まることもある、魔境とも呼べる最果ての地に自宅兼作業場を借りていた。
卓也は絶賛休職中で、朝の七時頃まで自作のボードゲームに関わるイラストやデザイン等を制作、気づけば寝落ち、といった寿命を捧げる生活を続けていた。
一方、明は転職前の有休消化に勤しんでいる。週末には一緒に活動している友人達も訪れるのだが、今日は珍しく家に二人しか居ない。
ただ、明の有休消化は今週いっぱいで終わってしまう為、卓也は最終日の今日ぐらい何か記念になるようなことをしたかったのだ。
が、別に何かが終るわけでも無く、何が始まる訳でもない。そんなとりとめのない思案が、炎天下に晒されぼんやりした卓也の脳みそを巡っていた。やたらとドス黒い排気で走る大型トラックが、猛スピードで卓也の横を抜き去っていく。
目の前に残された灰色の煙が薄れるまで、卓也は少しの間歩みを止めていた。今年で二十八歳を迎える自分の年齢に焦りを感じていないと言えば、嘘になるかもしれない。ただこの乗り掛かった船を降り、ファミリーカーに乗り換える勇気も、今からスポーツカーを吟味する気力も、卓也には無かった。
毎年のように耳にする親になった、やら結婚します、やらの報告は自分と別世界の話だと割り切って生きることに決めていた。
ただ、ああいった報告を受ける度「ああそうか、君はもうあの頃、あの日々から脱却したんだね」と穏やかに微笑む器量を卓也はまだ持ち合わせていなかった。
久しぶりに訪れるスーパーの内部は、空調が利きすぎていて、卓也は思わず銀行かよ、と呟きそうになった。そのわりに、と周りを物色しながら違和感を覚える。花火が安くなっている。もしかしたら今日は、世間的に夏が終わっていて、でもまだ外気は暑い、ちょうど境の時期なのかもしれない。
卓也は普段の食料調達はコンビニで済ますか、業務用のスーパーで買い溜めすることが多く、ろくすっぽTVも見ないため、世間の流れに疎かった。特に買うものも決めていなかったため、店内をウロウロ歩き回る。卓也の琴線に触れる代物はダブルのトイレットペーパーしかなく、手にとって帰ろうとしたところで、ポケットの携帯が震えた。
「烏龍茶 2L」
と、だけメッセージが届いている。明からだった。「了解」とだけ返し、飲料コーナーに戻った。レジに並んでいる途中、ふと近くの花火が視界に入る。先の会話を思い出したところで、一度列から外れ卓也は花火を見つめた。「すげー夏じゃん」と心の中で呟きながら、左手にトイレットペーパー、右手の烏龍茶を脇に挟み、空いた手で少し大きい花火の袋を抱える。
側から見たら滑稽だろうと感じた卓也は、カゴを持ちにエスカレーターの方へ戻るか一瞬悩んだが、そこまでの道のりを歩く間も滑稽だ、と思い直しそのまま列に並び直した。
「袋、どうしますか?」
「はい、ください。大きい方で。」
と、返したところで、レジのお兄さんの怪訝そうな表情に気づく。「ああ、そうか、大きい方のレジ袋といえど限界はあるのだ、トイレットペーパーも花火も入りやしない」と思考を巡らせたが、訂正するのも億劫だった卓也はお兄さんの表情には気づかなかったフリをして、烏龍茶だけを守るためには大仰で不釣り合いな大きさのレジ袋を受け取った。
結局、卓也は左手にトイレットペーパー、右手に大きな花火袋とこれまた大仰な大きさの烏龍茶のみ入っているレジ袋を持ち、なんかやっぱり滑稽だななどと思いつつ、帰路についた。
自宅に戻り、洗面所で手を洗っているところで、後ろから明がにゅっと顔を覗かせてきた。
「烏龍茶は?」
「あるよ、その袋ん中」
「おー、ありがと。何、花火でもすんの?デカくない?」
「うん、しようよ」
「いや俺はいいや、なんか外、虫とかいそうだし」
明のこの反応はあらかた想像はついていたものの、やはり面と向かって言われると、卓也の心には来るものがあった。
「外、虫いなかったよ」
「あ、そう?じゃあするわ」
そして、卓也は明が単純なことも理解していた。が、やけに聞き分けが良すぎる明を訝しく思った。そんな卓也をよそに、明が居間に戻りながら話を続ける。
「あのさー、あとちょっと話があんだけど」
嫌な予感がしていた。普段は他愛もない雑談をするときでさえ、人の目をしっかり見ながらする明が、やけに軽い口調で人の目を見ずに話し出すときは、大抵明にとって言いにくい、それでいて重大な話題であることが多かったからだ。そして、先のやけに聞き分けがいい明の態度もある。
卓也が居間に戻ると、明はタバコに火をつけ、梁の方を見つめている。
「何?」
「いや、あのさ、俺さー、あのー」
これは、相当言いにくい話題だな、と卓也は大袈裟に眉をひそめた。
「何だよ、もったいぶんなって」
「んーと、俺ここ出るわ」
晴天の霹靂という言葉が卓也の脳裏に浮かび、続けて、他にそういった意味の慣用句とかってあったっけかな、なんてどうでもいいことを思いながら様々な慣用句が卓也の脳を駆け巡っていた。
『青菜に塩、は違うか。馬の耳に念仏、も違うし、ていうか馬耳東風って方がかっこいいな、意味的には馬の耳に念仏と一緒だよな、あ、なんか耳って単語が入ってた気がする、うわー何だっけ。出てこないて出てこない、出そうなんだけどなー』
こうすることで、今の話を聞かなかったことにできるんじゃないか、という卓也なりの現実逃避でもあり、染み付いた癖でもあった。卓也が「耳」のつく慣用句を探しているところで、沈黙を消したい明が、さらに続ける。
「多分、10月とか11月ぐらい」
「何?彼女と同棲すんの?」
「まあ、そう」
「そっか、了解」
言いたいことは山ほどあったが、どんな言葉を探しても恨みごとのようになってしまいそうだった。ただ、彼を責めるのは違う、格好が悪い、卓也はその程度の分別は持ち合わせていたものの、大手を振って「応援するよ」なんて言葉を吐くのも白々しく聞こえそうな上、卓也のちっぽけなプライドはそんなことも許さなかった。
明は卓也の次の言葉を辛抱強く待っている。後頭部を掻きながら、卓也は悩んでいた、そして、ぶっきらぼうに口をつく。
「あれだ、寝耳に水だ」
「まあ、そうよな、すまん」
明に謝らせるつもりはなかった卓也は、ふつふつ浮かんでくる申し訳ない気持ちを消すために、自分の煙草に火をつける。長い沈黙が、空間を支配する。
「じゃあ、また色々進んだら、都度言うわ」
明は自らが生み出したその沈黙に流石に耐えきれなかったのか、徐に灰皿を持って椅子から立ち上がり、煙を漂わせながら自室へ続く階段を上がっていった。卓也は、今しがた自分の吐いた濃い白の煙と、だんだん薄い色に変わっていく明の残した煙とが、混ざっていく様子をただぼうっと、見つめていた。
どれくらい、そうしていただろうか。卓也はもう四本目を吸い終わる頃だった。明の残した煙はとっくに消えて無くなって、部屋には卓也の煙だけが充満していた。
部屋の窓を開けて、先ほどスーパーで買ったバケツ型の袋に入った花火を見る。まだ外は明るかったが、そこから卓也はそこから一つ、小分けになった袋を取り出した。まだ大量に花火の入ったバケツ型の袋が部屋には取り残されていた。
その花火がどんな風に光るか、卓也にはよくわからなかったが、大きな袋と比べて、そのちっぽけな小さく細長い袋だけを持って玄関へ向かった。そこで、普段明が使っている土の茶色が染み込んだサンダルが目に入る。卓也はそのサンダルを視界から振り切るように、外に出た。
本来ならば小さい蝋燭に火をつけたり、水を入れたバケツを用意したりなど、花火のための準備がいることを卓也はわかっていたが、今はとにかく心にぐるぐるめぐって収まらない灰色の小言たちを取っ払いたかった。慎重にライターから花火へ火をつける。予想以上に大きな音とともに、安っぽくも派手な光の束が吹き出る。
「これはあれだな、あの花火ちょっと多すぎたかもな」
誰に向けるでもなく、強いて言えば卓也自身にそう言い聞かせるように、納得させるように、口に出した。すぐに一本目の花火は終わり、焦げ滓がアスファルトに、ぽとりと落ちる。その様を自分に重ねていると、花火の寿命の短さや明の先程の告白に対して、ふつふつと灰色の小言が卓也の心を巡り出した。
そんな風に右手の燃え滓を睨みつけていると、がらがらと音を立てて玄関の引き戸が開いた。
「何だよ、花火やるなら言えよー。てか、まだ外明るいじゃん、あ、ほらやっぱ水用意してない!卓也それはダメだろー、え、うわ何、卓也お前ライターから火付けたの?あっぶな!」
水の入ったバケツと、バケツ型の花火の袋を自分の脇に置いて、明が踵にサンダルを嵌め直しながら捲し立てる。卓也は明のその姿を見て、目を輝かせてしまったことを少し恥ずかしく思った。そうだ、明はこういう奴だった、と卓也は思い直す。
「なんか、この花火めっちゃ終わるの早いわ」
「いいじゃん、まだこんなにあるんだし!」
「まあ、そっか」
卓也は「今この瞬間だけは、全部を飲み込んでただ明るく照らしてくれ花火よ」と何かの歌詞にありそうな台詞を頭に浮かべた。そう、願わずにいられなかった。外はまだ明るく、夜はまだまだ長い。卓也と明の頭上では、門灯が輝いていた。
「なあ明、今アツい感じのお笑い芸人って誰?」
「え、なんだよいきなり。何?お笑いに興味出てきたん?沢山居るから、あとで纏めて動画のURL送るわ!」
「いや、やっぱいいわ」