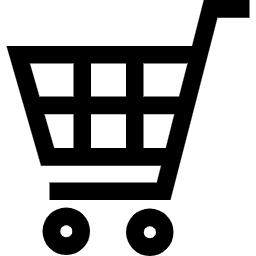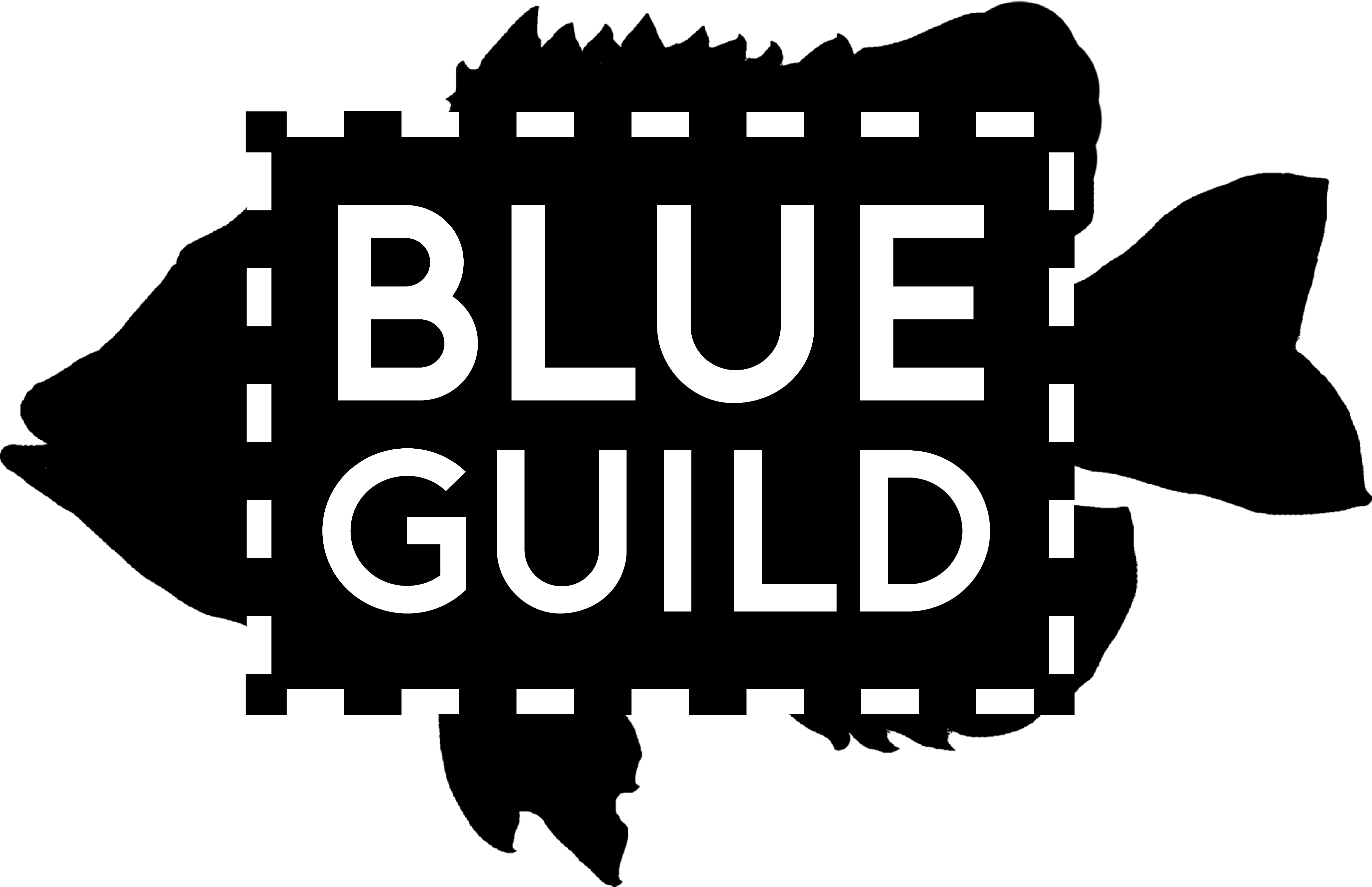
スーツケースが重い。何を思って先人はこんな丘の上に家を建てることにしたのか。私には理解ができない。
先人と言っても私の祖母だ。
父方の祖母が亡くなった。両親共に私が中学生の頃に逝ってしまったので、この祖母が私の育ての親だった。
嫌いだった。
嫌いだったけれど、お金だけはあったのだ。だから、こんな港が一望できるような丘の上に家を建てた。
「昔は運転手がいたんだよ」と、祖母はよく言っていた。だからどうした。私は今を生きているのだ。家を引き継ぐこの身にもなってほしい。
いくら遺言でも、この坂はちょっと辛い。
それに何もこんな夏終わりに逝かなくても、と心の中から湧き出てくる様々な愚痴を飲み込みながら、飲み込んだ分だけ噴き出る汗と共に私は登る。
夏が終わりに近付いているとテレビで三木さん言っていた。学生の頃から嘘つきだったけれど、公共の電波で嘘をつかなくてもいいではないか。
たいして仲も良くない、どちらかというと嫌い寄りである大学時代のクラスメイトの顔を浮かべて呪詛を吐いていたら、ようやく家の前に着いた。
案外、この家の門ってそんなに大きくなかったんだ。
叔父さんたちが先にお葬式の準備をしている。優里奈から、田舎独特の面倒臭さをよく聞くけれど、ここは都会だし、みんな都会人だ。
だからこそ面倒なこともある。
「沙理ちゃんはどこの大学だったのかしら?」
「沙理ちゃんってどんなお仕事しているの?」
「最近の子って、結婚が遅いらしいわよねぇ」
「働きづめていたら、婚期逃しちゃうぞ~?」
「ねぇ、京都の男の人たちってどんな感じ?」
などなど。
金持ちたちによる見栄の張り合いには飽きた。だから私はこの家を出て行ったのに。
周りの反応は予想通りだった。一言一句とは言わないけれど、ある程度路線は同じ。
結婚。
仕事。
学歴。
その類の話を、よくもまぁ飽きもせずしていられるものだ、と感心してしまう。
どうせなら、冷房の効きが悪いあの家で引き籠っていればよかった。
こんな話を聞くために、私は残る夏の丘を、喪服の入った重いスーツケースを運びながら、登ったわけでは無いのに。
というか、そもそも何のためなのだろう。
何故、私は大嫌いだった頑固者の祖母を参る為に帰って来たのだろう。
仕事を始めて二年が経って、嫌な上司もでき、既婚者からのセクハラまがいの扱いを受け、それでもなんとか生きているとは言えない毎日を暮らしていることに嫌気がさしたのだろうか。
そんな感傷的な女ではなかった気もする。
年取ったってことかな、なんて言ったら会社のお局に殺されかねない。人のお葬式の日に、自分の死なんて考えたくもない。
要は、成長したのだろう。
大人になった、ということなのだろう。
そもそも大人ってなんなんだ。
そんなことばかり考えていたら居心地が悪くなって、持ち前の愛嬌を発揮したちびっ子たちの相手にも飽きて、熱中症にもなりたくなくて、日焼けもしたくない私は、葬儀場の喫煙所で煙草を吸う。
隠れて煙草を吸っていたところが見つかり、祖母にぶん殴られた記憶が蘇る。
反抗して家出したなぁ、と恥ずかしくて死にそうになる。あれもこんな夏の終わりの時期で、でもあの頃は今よりも涼しかった気がする。
一人で思い出し笑いをしていると、眼の前に女の子が現れた。こちらを見ている。
単純に恥ずかしい。
祖母は一丁前に書道教室みたいなものを開いていたので、そこの生徒なのだろうか。
小学四年生くらいだろうか。すらりとしていて、背が高い。それなのに顔が幼いので、妙にアンバランスだった。
流石に悪いかと思い、煙草を灰皿に押し付ける。「どうしたの?」と声を掛けようとしたところで、踵を返して建物に戻ってしまった。
なるほど。持ち前の愛嬌は小学生には通用しないらしい。
建物に入ると、冷房が気持ちよかった。九月二十日にもなっているのに、この暑さはなんなのだろうか。
シャツの内側にたまる汗に不快感を覚える。
地球を恨んでも仕方がないので、嘘つきの三木さんを恨むこととする。
まぁ、彼女だってそんなことを言われる義理なんて無いだろうけど。
階段の近くに、またあの女の子の姿があった。こちらをちらりと見て、そして階段を上っていく。制服を着ているということは、それなりに良いお家のお嬢さんなのだろう。
興味が湧いた。
祖母がそれなりに慕われていたことは、今日の弔問客の多さから分かった。ただ、その中でも際立つ彼女の存在が、私に興味を湧かせたのだ。
彼女の後ろをついて、階段を上る。何も言わずに私をちらちら見ては、彼女も階段を上っていく。
「着いてこい」と言わんばかりだ。
二階につくと、彼女は右に曲がった。手すりから私を見下ろして、小走りで進んでいく。
そのときに初めて、しっかり目が合った。
夏の終わりを告げてくれるような冷たい視線で、私の背中に嫌な汗が垂れるのを感じる。その汗はさっきまでのものとは違った。
暑いのか寒いのか分からなくなってきた。
二階について、私は彼女の後を追う。
行きつく先は、屋上だった。屋上を開放している葬儀場というのも、直結でいいなぁなんて不謹慎極まりないことを考えながら、彼女に遅れて私も屋上に出た。
先を見ると、見慣れない女性がいる。小綺麗な喪服を着ているけれど、太陽が眩しくてなかなか顔が見えない。
女の子は、その女性の隣にトタトタと小走りで向かうと、何かヒソヒソと話しかけた。
そして、女性がこちらを向いてぺこりと頭を下げる。
私もつられて頭を下げてしまう。
少しふくよかなその女性は、少しずつ私に向かって歩いてくる。女の子も、少し後ろについてくる。
近付いてきて、徐々に顔が見えてきた。
あぁ、この人か。
「この度は、ご愁傷様でした」
「あぁ、どうも。こちらこそ暑い中ご足労いただき、ありがとうございます」
こんな挨拶もできるようになってしまった。
大人になるってこういうことなのだろう。
こんな相手にでも、こういった類の「ご挨拶」ができてしまうのが大人なのだろう。
この人は、私のお父さんの不倫相手で、そして私の両親が逝ってしまった遠因。
私のお母さんは、世にいう肝っ玉母ちゃんで、不倫現場に車で駆けつけて、この女性とお父さんをその場で引っぱたいて、そしてお父さんを連れて帰っていた。そして事故は、その帰り道に起きたのだ。
運転していたのはお母さんで、対向車線からトラックがはみ出てきて、即死だったという。
「えっと」
それらを一気に思い出して、言葉が詰まる。残暑の日差しが鬱陶しい。嫌な気持ちになるために、女の子を追いかけていた訳ではないのだけれど。
「この子に、お祖母ちゃんを見せてあげたくて」
少しふくよかだけど、凛とした顔立ちで彼女はこう言った。
目の前が真っ暗になるとはこのことなのだろうか。これが熱中症から来る眩暈であればどれほど良かったことか。そして顔が引きつる。引きつっていることが分かってしまうくらいには冷静なのだけど、ショックで倒れそうになる。
そう、私は今ショックを受けている。
ただ、ショックを受けていると自認できている冷静な私も、居合わせている。
行き過ぎた衝撃はこうも人を惑わせるのか。
冷静な私に意識を委ねつつ、女の子を見る。
なるほど、私が十五の時に死んだんだ。他でこさえた子供ならこれくらいの年齢にもなっているか。
「こんなこと、許されることではないと分かっているのですが」
「えーっと」
言葉に詰まる。感情の逃げ場を求めて隣の女の子を見ると、唇を喰いしばり、拳を握りしめ、そして自分のお母さんから目を逸らしている。
頭を下げ続けるお母さんの横にいる子供という存在ほど、惨めな生き物もなかなか居ない。
そりゃ、そういう顔にもなる。
「そうですね。この子には、何も罪は無いですから」
私はそれだけ言って、女の子に近寄る。
少しビクっとしたけれど、私から目を離さない。この気の強さはお父さんには無かったなぁ。似ている訳は無いのに、私はお母さんを思い出す。
そうなると、この頭を下げ続けている女性も、案外肝っ玉母ちゃん気味なのかもしれない。
屋上にいるのも、そのプライドなのか。プライドが高いから、屋内にいることができない。周りの目が、気になって。暑いのに。
そこまで考えていたら、今は亡き父親の、好みの系統がこのタイミングで分かってしまって噴き出す。
よくよく考えたら一階で横たわっている祖母も強い女だった。
あの父親、さては性根はマザコンだったのか、と思うと更なる笑いがこみあげてきてしまった。
突然笑い始めた私をみて、女の子もその隣の女性も不可思議なものを見ているような顔で私を見た。
精一杯の余裕を示すように、私はその子の横にしゃがみこんで言う。
「別に取って食うわけじゃないよ。私は沙理。一応お姉ちゃんってことになるのかな」
「あなたの、お名前は?」
☆
「おねーちゃーん! もう八時だよ!」
一階から芹那の声が聞こえる。相変わらず冷房の利きが悪い家なのに、よくもまぁこんなに熟睡したものだ、と目覚めと共に汗だくの私は感心する。
ていうか、夏は終わったんじゃないのか、三木さん昨日言ってたじゃん。また嘘ついたのか、あの女。
「はーい」
多分聞こえてないだろうな、という返事をする。おそらくあと五分でもしたらドタドタという足音を立てて我が義妹が起こしにきてくれることだろう。
私は無事三十路に突入した。そして三年前に京都から、本格的に地元に戻ってきた。
その理由は芹那だった。
小学生のときまで地方の国立大学付属の小学校に通っていた芹那が、中学受験でこの家から歩いてすぐの学校に合格したのだ。シングルマザーの香苗さん(父親の不倫相手)と共に引っ越して来る予定だったのだけれど、直前で香苗さんのお母様が体調を崩してしまったらしい。
だから、私から提案したのだ。
「祖母ちゃん家に、一緒に住まない?」と。
ドスドスという足音が聞こえてくる。身体は細いのに、足音は五月蠅い。それとも家が古いのか。
「起きて! もう私学校行っちゃうからね!」
「はーい……」
布団に潜りながら返事をする。
「もう、知らないから!」
部屋を出て行こうとする芹那の背中に声を掛ける。
「芹那、今日の放課後、覚えてる?」
「起きてんじゃん。なら早く降りてきてよ朝ごはん冷めちゃうよ」
起き上がって、芹那を見る。
目が合う。
相変わらず凛とした目をしている。力強いその目は、出会った日を思い出させる。
「お祖母ちゃんのお墓参りに行って、そのあとご飯食べに行くってやつ?」
「覚えてるじゃん、偉いね」
私はベッドから降りて、芹那と共に一階に向かう。
「朝ごはん、ありがとね」と玄関で芹那に声をかける。
「まあね。それじゃあ、いってきまーす」
今日は芹那に出会った日と同じ、九月二十日。
なかなか終わってくれない夏を引っ提げて、私の母校の制服を着て、あの頃の私と同じ十五歳の芹那が、トットットと軽い小走りで家を出て行く。そしてその背中を、キラキラと照らす日差し。
残る夏は、もう僅か。