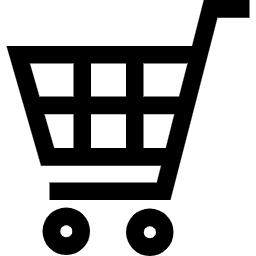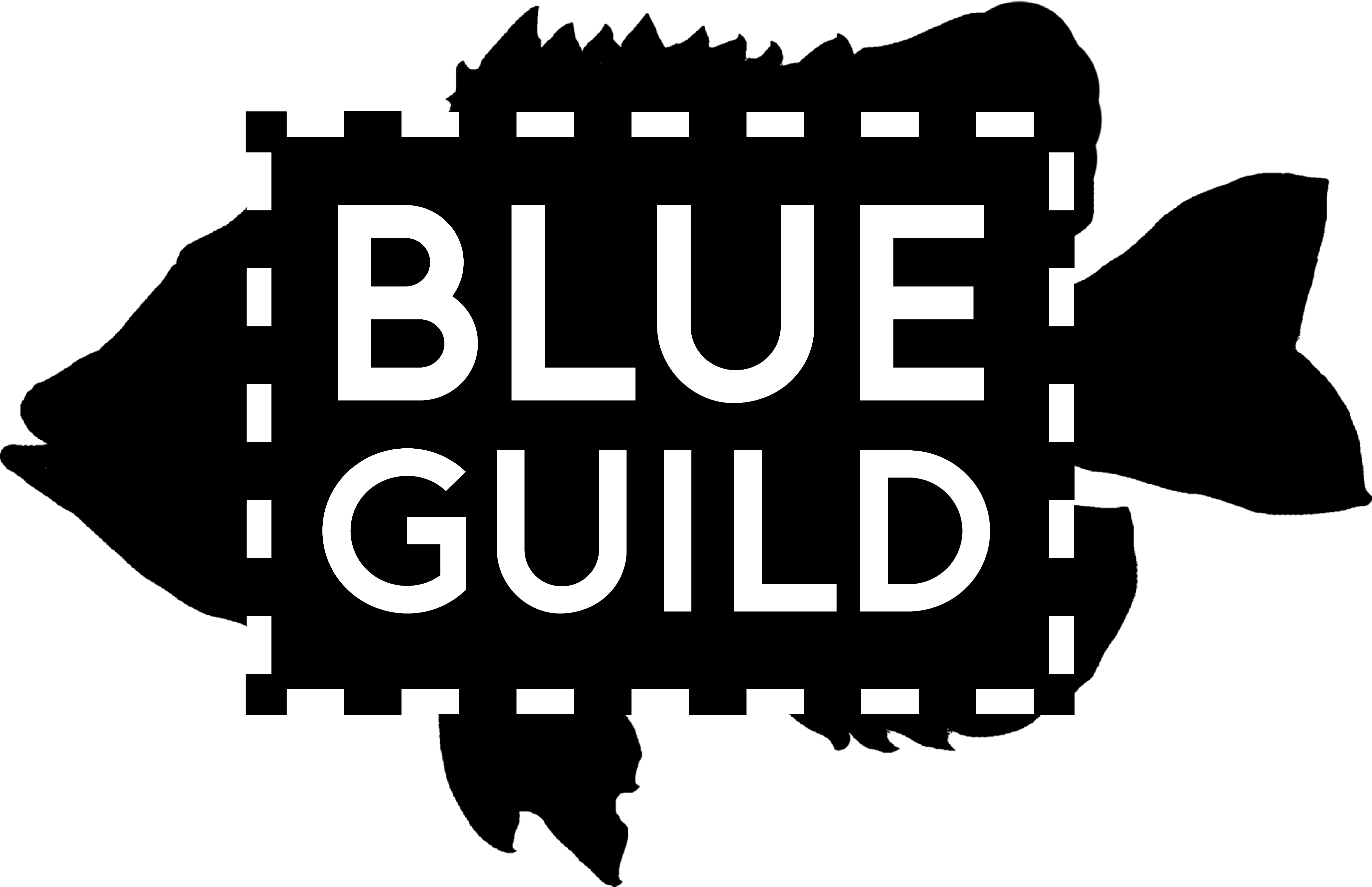
九月。私はこの月が嫌いだ。
何故なら、ここから冬に向かうから。
秋分の日を境に、日の出日の入りの時間が入れ替わっていく。それは、冬に向かっていくことを表していて、すなわち夜が長くなることを示す。私は、夜が嫌いだから、この季節を恨めしく眺める。眺めるしか、できることは無いから。
幼い頃は、来る朝よりも去り行く夜を愛していた。朝に弱かった私は、朝の到来を憎しみ、夜の持続に心を躍らせていた。なにより、夜は美しくて、神秘に満ちていて、優しかったのだ。
ある日、唐突に気付いた。朝が来て、夜が来て、そして朝が来るという当たり前のサイクルに気付いてしまった。
そして私は、朝の到来の前にある夜に、問うた。
「なぜあなたは去り行くのか」と。
「なぜあなたはいなくなってしまうのか」と。
すると夜は答える。
「良い子で待っていれば、また会えるさ」と。
だから、私は良い子で待っているようになった。
家のお手伝いにも、学校での生活にも、習い事にも、精を出した。そうしていれば、夜がまた来てくれると感じていたから。
眠りが深いから、朝は辛かった。だから、朝が嫌いだったのだ。でも、朝嫌いはある日突然変わった。
それは、夏の日。
夏は、日が長い。何時まで経っても、どれだけ良い子で待っていても、夜が来ない。そしてせっかく来た夜が、短い時間ですぐいなくなってしまう。今思えば、それがこの地球という惑星の、日本という土地に与えられた運命のようなものなのだけれど、あの頃の私は、それを運命だと信じ切るにはまだ子供すぎた。
そして子供すぎた私が、ひどく落ち込む事件が起きる。
前日、あまりにも夜が心地よくて、私は随分長い間共にいた。幼いながらにも一度来た夜が、すぐに去ってしまうことに気付いていたので、尊い夜を慈しむような気持ちだった。眠る直前に、嫌いな朝が来て、夜が撤退していく。そのことに目を背けるように私は眠った。
眠たい目をこすりながら共に過ごした夜が、また到来してくれることを信じて私は眠った。
そして、学校に行く。学校はちゃんと始業から行かなければならなかったので、朝お母さんに起こされたときは、この世の地獄なのかと思うほど、眠たかった。
身体が重くて、頭がぼーっとする。それでも私には、夜がいてくれる。そう思っていたのに。
眠りそうになる自分に鞭を打って、学校生活を終えた。その日は習い事もなかったので、家のお手伝いという名の浴槽の掃除だけして、私はふらふらになりながら部屋に戻った。
そして、夕暮れ時に、もう少しで夜が来てくれるというタイミングで、私の体力は途切れた。
目を覚まして、外を見ると、もう夜は退却していて、朝が襲来していた。
「やたらぐっすり寝ていたから、起こさないでおいたわよ。はい、朝ごはん。せっかく昨日キョウコが好きなハンバーグにしたのに」
お母さんは、やすらかに眠る娘を邪魔しないでくれていたのだろう。
ただ、私はその日、ひとつの夜を逃した。
そのことにひどく落ち込み、自分勝手に、夜を恨んだ。
「良い子にしていたのに」
「一生懸命頑張って一日を過ごしていたのに」
「約束したのに」
そして、私は夜に裏切られたような気持ちになって、その気持ちは芽生えたあと大きく育って、私の心に住み着いた。
こうして、私は夜が嫌いになった。
部屋の窓から、外を覗く。今の時間は夜で、輝くネオンに目をとられながら、高速道路の渋滞に蠢くランプの線を指でなぞりながら、私は昔を思い出していた。
思わず昔の私の自分勝手さに笑ってしまう。なんだか思い出し笑いのようで、恥ずかしい。
「なんか……面白いことでもあった?」
私の後ろに立っていた戸張さんが、窓の反射で映っている。
反射する彼に、私は答える。
「ふふ……なんでもない、かな」
一連の交わりを終えて、シャワーも浴びて、私たちにはあと眠ることしか残されていなかった。
ベッドのシーツは美しく乱れていて、その上に横たわる戸張さんの隣に、私は潜り込む。
「三連休の最終日くらい、おうちに居なくていいの?」
「いいさ。それに今週の木曜は秋分の日で休みだ。その日に家族サービスするよ」
「羨ましいなぁ、奥さん」
戸張さんがまとう空気が変わる。なぜなら私は普段、こんなことは言わないから。
営業部ナンバーワン成績で、胸板が厚く、家族を大事にしていると噂の男に、都合よく抱かれている女でしかないという自負はあるので、普段は絶対にこんなことは言わない。
言葉にして、私が驚いたくらいには。
「どうしたの?」
じゃれるように、はぐらかすように、私と枕の間にたくましい腕を通す彼の仕草が急に億劫になった。その仕草に対して私が行動を取ることが、億劫になってしまった。
さっきまで、昔のことを考えていたからだろうか。これから来る、大嫌いな夜が続くはじまりの日である、秋分の日に対しての意識が私の中に強く残っていて、話題に出たから、思わず口走ってしまったのか。
私は、驚きと戸惑いに振り回されつつ、絞るように、気丈なフリをして、「ううん、なんでもない」と答えて目を瞑った。
夢を見た。幼い頃の私が目の前にいる。空に向かって何かを話しているその姿は、覚えがある。
あれは、夜と話している私。
「どうしたら、また会えるの?」
「良い子にしていれば、ね」
低い声が脳内に響く。
「でも、キョウコ、今日習い事もがんばったし、おてつだいもした」
「偉いね。それに、良い子だ。でも、それは今日こうやって会う為の分だ。明日も同じようにしないとね」
「わかった!」
私と夜の会話が脳内で繰り広げられている。
あぁ、そうだった。私はこんなにも夜が好きだったのに。
好きだったのに、嫌いになってしまった。
そう考えたら、急に場面が変わった。
私は大学生になっていた。この部屋は、確か二か月だけ付き合った月島くん。こんな顔してたっけ。あんまり覚えていないのに、こうして夢に出てくるんだから不思議。
私は、夜が嫌いになって、それは自分が思っていた以上に心の中で大きく育っていて、だから夜を独りで過ごしたくなくて、色々な家に転々としていた。
そのうちの一人が月島くん。なんの授業かは忘れたけど、隣になって、連絡先を交換したらすぐ私は月島くんの家に転がり込んだ。抱かれている間は、夜も朝も無いから、私にとっては都合が良かった。
気付くと、私は社会人になっていた。
あれは同じ部署の黒沢さんだ。入社半年で、関係を持つことになった課長。黒沢さんは、私との関係を1年くらい続けた直後、しれっと結婚をした。
同じ部署の凪ちゃんと。
凪ちゃんとは仲良しだったから、私は黙っていた。結婚式にも呼ばれたし、ちゃんと親御さんへのスピーチで泣いたし、完璧に黒沢さんとの関係は断ち切って、匂いすら漂わせなかった。
その結婚式は、九月だった。
景色がふっと変わる。やたらと着飾った私が夜の道を歩いている。あの紙袋を持っているということは、凪ちゃんの結婚式の帰り道だろう。
何度も、ハンカチで顔を拭っている。泣いているのだろうか。そもそも私はこの日の帰り道、泣いていただろうか。視界は私の後ろ姿しか捉えていないので、泣いているのか分からない。泣いていたのか思い出せない。
二日後に、私は戸張さんに抱かれることになる。
夢の移動が終わって、目を覚ました。
隣ではまだ戸張さんが眠っていて、大きな窓の外は少し明るくなりはじめていた。
私はするりとベッドから降りる。
重さが急になくなったからか、戸張さんが寝返りを打った。
窓の縁に腰をかける。
夜の淵を指で撫でる。
追いやられている夜に話しかける。
「ねぇ、お久しぶり。今の私は良い子かな?」