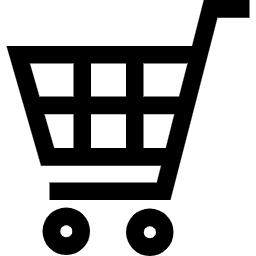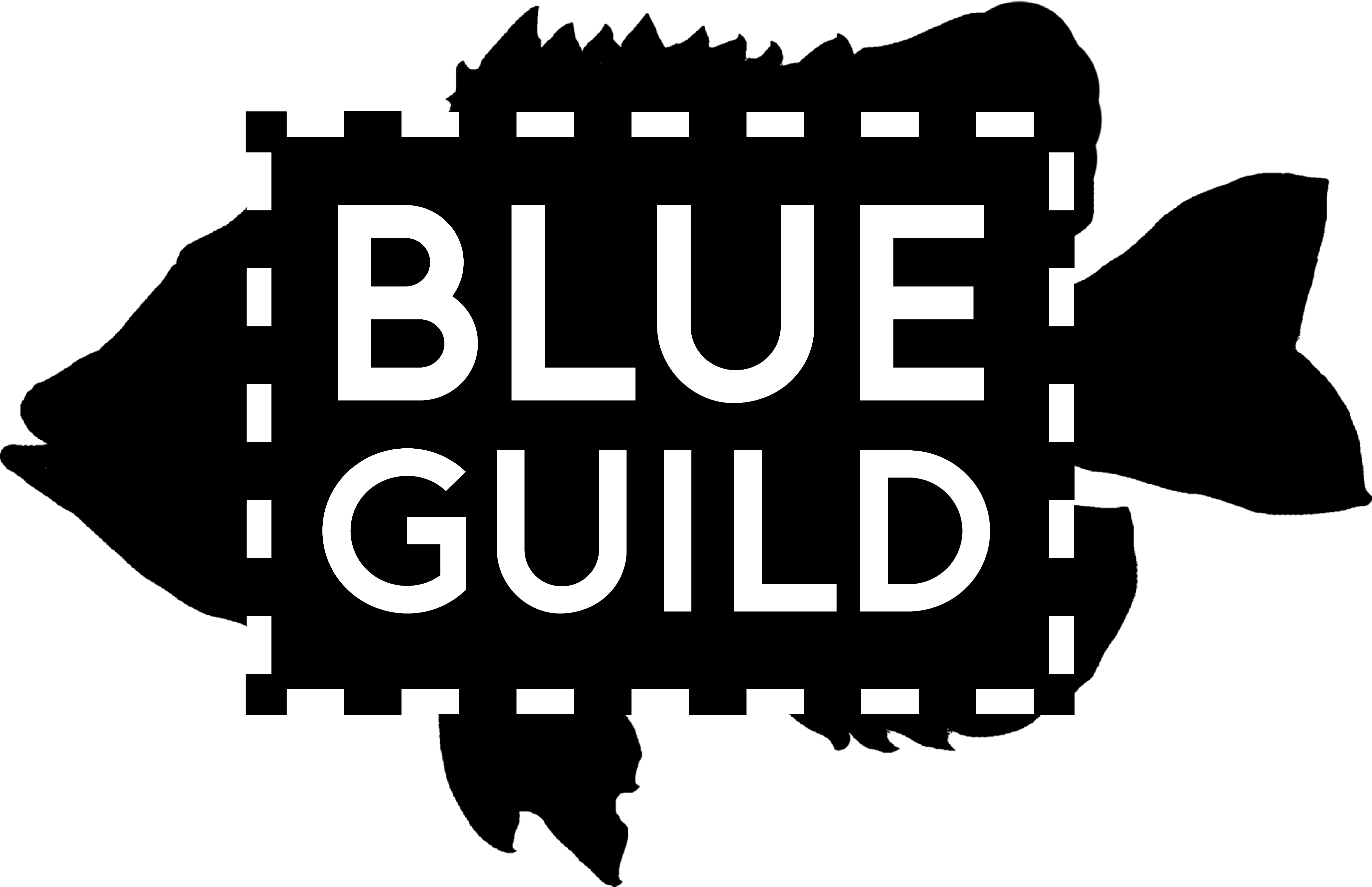
夏の終わり、庭園に朝の陽光が差す。
私、アリシアは、その陽の光で目を覚ます。
眠たい眼のまま、窓を開ければ、乾いた風が入り込む。
木々が風にさらわれていく音で、ゆっくりと覚醒した。
9月のヴェネツィアは、庭園で紅茶を飲みたくなる季節だと思う。
ティーポットにお湯を入れ、茶葉が沈む時間を、私は楽しむ。
見渡せば、庭を彩るユウセンギクの花。
庭園を流れる何本もの水路と水の音。
それらを感じながら、紅茶をティーカップに注ぐ。
ボローニャから取り寄せたアールグレイの茶葉の香りは、私の頭をすっきりさせてくれた。
ここは、裏側のヴェネツィア。
表のヴェネツィアからは、特定の社を通してしか行き来でない場所であり、
私はこのヴェネツィアの守護者として、この庭園に住んでいる。
表側の世界が、人類の進歩と共に知識体系を先鋭化させていく場所だとすれば、
この裏側の世界は、人類の知識体系の中で、不要になったものを再利用、そして別方向へと進化させていく場所である。
古代の自然科学、哲学から、魔術、妖術、呪術、そして神の奇蹟まで。
人類が不要と断じた文明の集積地。
そうしたものを利用して、裏側の世界の人々は暮らしている。
その中でもこの水の都は、住んでいる私が言うのも何ではあるが、
とっても美しい都市国家(ポリス)だと思うのだ。
この都市ができて既に1000年以上。
表側で不要とされた知識の種は、芽となり、そして今や花となり、
水の都を彩っている。
で、そんなところで私が何をしているのかと言われれば、
庭園の管理と、この庭園の奥に祀られている、神様への奉仕である。
だから、周りからは守護聖人と言われているけど、半ば巫女としての仕事も入っていると思う。
ただ、そうした神事は、大体午前中のうちに終えることができるようになっている。
午後には会わないといけない人が一人と、会いたい人が一人いたので、
いつものように、テキパキと仕事を終え、街へ繰り出すことにした。
庭園は、この都市国家の中でもさらに秘匿された場所にあり、
決められた道を決められた順番で通らないと、辿り着けない場所にある。
この決まり事は、守護聖人である私と、この都市国家の上のお偉い方だけが知っていて、それ以外の人たちは、基本的に入ってくることができないようになっている。
西欧全土に広がる童話の雛形。呪術的逃走の逸話をベースに組まれた儀式的結界ではあるが、ここでは細かい話は割愛しておこう。
その決められたルートを出て、街を巡る。
目的地はこの都市の中心にある大聖堂ではあるが、その中途には、魚市場や食堂、服飾店などがあり、人通りがとっても多い。
「あら、アリシア様、今日も大聖堂に行かれるのですか?」
「アリシア様、海で美味しい魚が取れたんで一匹どうですか?!」
「うちの店で昼飯食ってかねえか、アリシアの嬢ちゃん!」
と、道ゆく人に声を掛けられる。
うん、今日もみんな元気そうでよかった。
何分ここの守護聖人なんてものをやっているので、こうして、皆の顔を見ておくのが私の日課の一つなのだ。
「アンネッタさん、そうなんです、ちょっと呼び出しをもらいまして。あっ、ブラウンおじさん!サーモン一尾もらえますか!用事もあるので、氷入れていただけると!カルロさん、すいません今日予定が先に入っちゃって、また今度食べさせてください!」
人々の喧騒と波の音、カモメの鳴き声が入り混じった、賑やかな夏の終わり。
それがこのヴェネツィアの日常である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヴェネツィアのサン・マルコ寺院。
通称大聖堂は、このポリスで一番巨大な建造物である。
広間は昼も夜も人々の往来が止まることはなく、この街の象徴と言ってもよい。
その建物の一番上部、大鐘楼前で、私を待つ人物がいた。
「ご無沙汰してます、賢人トロイメライ」
「おお、待っておったよ、聖人殿」
そこには、黒いローブに白髪、腹先まで伸びた長い髭という、魔術師然とした見た目の、
柔和な雰囲気を醸し出している老人がいた。
「もしかして、お待たせしてましたか?」
「いや、儂も今来たとこじゃ。あまり気にするでない」
このお方、そこそこの頻度で私を呼び出すことのだが、
待ち合わせ時間よりどれだけ早く来ても、彼の方が先にいるのだ。
大鐘楼に住み着いているんじゃないかとたまに思ったりする。
「何か言ったかね?」
「いえ、トロイメライさんが大鐘楼の妖精だという与太話も、あながち間違ってなさそうだなと」
「ほっほっ、このボケ老人が妖精とは、些か荷が勝ちすぎてるというものよ」
「それは自虐が過ぎてませんか、賢人殿」
ーーーこのヴェネツィアという都市国家を運営する最高機関の名を、【夜明け前の会議】という。
その会議に参加するのは、この都市のトップである哲人王と、王をサポートする七人の賢人たちである。
目の前にいるこの白髪の老人は、都市国家を運営する七賢人の一人であり、高名な占い師でもあり、世界で現存する魔法使いの中で、五指に入ると言われている。
なので、ある意味この都市国家においては、伝説的な立ち位置のお方ではあるが、私は守護聖人となった始めの頃から、今まで幾度となく顔を突き合わせており、賢人というより、やや遊び心が過ぎているおじいちゃん、という認識である。
「で、本日はどのような御用で?」
「おぉ、そうじゃったな」
と、ゴソゴソとローブの中から、一冊の本が出てきた。
「これをアリシア、君に渡そうと思っての」
「これは、、、?」
「儂の日記じゃよ」
「・・・」
「・・・」
エメラルドグリーンの瞳が私を見てくる。
いやでも、こんな微妙に反応に困るもの渡されてどういえば良いのか。
まあ、この賢人の日記ともなれば、公開するだけで人が殺到しそうだけど。
「冗談じゃよ」
「冗談かい」
「とはいえ、あながち嘘っぱちではないのじゃ。
守護聖人アリシアよ、これは何だと思う?」
と、急に賢人っぽいトーンになった魔術師が、私に問うてきた。
「・・・グリモワール、とか?」
「正解じゃよ、それも、世界がひっくり返る魔法が記録されておる」
「・・・」
沈黙の質が変わる。
聞いて、思わず眉間に皺が寄った。
そんなものを私に渡そうとして、一体何を企んでいるのかが、さっぱり読めなかったからだ。
「いや何、日記というのは間違いではなくてな。
ここに書かれている魔法は、儂が長年かけて開発した、言わば研究成果みたいなものじゃ。」
「どんな危ない魔法を研究してたんですか」
「まあそう言うな。本の形になっているとはいえ、今のお主には読めぬじゃろうしの」
そう言われて、その表紙が真っ黒な本を、押し付けられた。
中を開いてみると、確かに何も書かれていなかった。
このおじいちゃん、もしかして私をからかってるだけじゃなかろうか。
「なあに、時期が来たら読める」
「いや、そもそも私の専攻は魔術でも魔法でもなくて、神術や奇蹟寄りなので、読めたところで使えないと思うんですが・・・」
「知っておるよ。それでも、その本は君が持っていなければいけないものなのじゃ」
「・・・わかりました。そこまで言うなら、ありがたくもらって置こうと思います。ただ、そもそもこれ、祭政不干渉に引っかかりませんか?」
祭政不干渉とは、その名の通り、神事を行う守護聖人と、政殿を行う夜明け前の会議の間で、権力による干渉を禁ずる、と言う決まり事である。
要するに、賄賂を禁じ、権力が一箇所に集中するのを防ぐ内容である。
まあ、守護聖人は私一人なので、事実上は私一人の治外法権、といったところであるが。
「大丈夫じゃよ、ついさっき、儂は七賢人を辞めてきたからの」
「はっ・・・?」
何かとんでもない爆弾発言が聞こえた気がする。
「いや何、その本に書かれた魔法を研究する中で、ちょっとこの世の真理に触れてしまっての。おかげさまでちょっと旅に出ないといけなくなってしまったという訳じゃ。それで、七賢人を辞める必要が出てきての。」
「いやいや」
「何、既に会議での承認は貰っておる。あとは、儂が旅に出ている間、儂の大事な子供達(研究成果)を預かっててくれる者が必要での。そこで君に白羽の矢が立ったのじゃ。君なら、他の賢人の干渉から、その本を守れるだろうしの。」
「いや、それはまあ、確かに・・・」
私はこの数分の間に、何度「いや」という言葉を使ったのだろうか。
ともかく、毎度毎度素っ頓狂なことをするおじいちゃんだと思っていたけど、今回のは明らかに過去一とんでもないことをしているのは、私からしても明らかだった。
「というわけで、儂はもう出なければならん」
「行動早いですね相変わらず」
「何、今日できることは明日まで延ばすな、じゃよ」
「思い立ったら吉日ってやつですか」
「それは東洋の言い回しじゃな」
「はい、最近東洋人の友達ができたので、ちょっと覚えたんですよ」
「ミロク君じゃな。」
「知っていたんですね」
「無論、識っていたとも。彼女のことも含め、今年からしばらくは、世界が賑やかになるのう」
この老人が言う、賑やかは、おそらく洒落ではない規模だと思う。
これは、外したことのない私の勘が告げている。
今聞いておかねば、後々てんやわんやすることが目に見えている。
私は、機を逃さず質問することにした。
「・・・世界、とは?」
「君には、できれば自分の目で確かめて欲しいんじゃがの」
「当代一の占い師に言われたら、気になって夜も眠れないですよ」
「それを自ら経験することが、人生における一番楽しいことなのじゃ。
とはいえ、お主の立場もある。土産としていくつか置いておこう。
そうじゃな。例えば、ゲルマンの奥地で、夜の領域が発生しているという話を聞く。
それから、東方の華胥の楽園が、西欧の方に近づいて来ているとも。
また、アルプスの妖精竜。ここ最近活動を活発化してきているらしいしの。」
「どれもこれも童話レベルの話ですね・・・。本当にそれが、連続して起きるんですか?」
「プレゼントはここまでじゃ。これ以上はお主たちの目で確かめるとよかろう」
「そうですか。・・・いえ、ありがとうございます」
「何、お主にとっても楽しい時間となるだろうよ」
「そう言ってもらえると、少しは気が楽ですね」
「さて、そろそろ儂は行かねばなるまい」
「ほんとにすぐ行っちゃうんですね」
「左様。なあに、またどこかで会える。それまで、君がどのような経験を積むのか、楽しみに待っておるよ。」
そう言って、老人はその場から、霞のように、消えてしまった。
一人残された私は、預かった本を持ったまま、静かに大鐘楼の鐘の音を聞いていた。
窓を見上げると、秋空は青く、高く澄んでいた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この水の都は、慣れないものにとっては天然の迷路であり、慣れたものにとっても、ふと自分の知らない道を歩こうとすると、方向感覚を持っていかれてしまうことで有名である。
その街の迷路の奥も奥にある、一件の石とレンガ造りのアパート。
その一階には、こじんまりとしたカフェがある。
地元住民でも中々辿り着けない、知る人ぞ知るそのカフェの名を、イルジオーネと言った。
ここに私の会いたかった人、私の懐刀が住んでいる。
「だーれが懐刀よ」
「あら、心の声が漏れちゃったみたい」
と、目の前でムスッとした顔でこちらを睨んでいる少女の名を、ミロク、と言った。
「まあまあ、そう言わずに。はいこれ、お土産のサーモン」
「あら、気が利くじゃない」
と、急に顔を明るくさせるミロク。
うん、この子は素直で見てて安心する。
女の子なのにキリッとした顔立ちだったりするのだが、食べ物に目がなく、欲求に忠実な犬みたいな子だなぁと思っていたりいなかったり。
「ヨハネさん、お邪魔します」
「まさかまたアリシア様がこんな場所に来てくださるなんて、およよよよ、、、」
「何回泣けば気が済むのよ・・・」
ここのマスターはヨハネさんと言って、メガネをかけた優しそうな男性だ。
私がこのカフェに来るたび、とっても喜んでくれるのだけど、
私から見ても、ちょっと気が弱そうに見えてしまい、我が強いミロクに振り回されてるんだろうなあと思う。
まあ、ヨハネさんはどう見てもM気質なので、上手くやってるのかもしれないけど。
「ヨハネ、今日の夜はこれでよろしく。あとレモネードちょうだい。二つね。」
と言って、ミロクは彼に向かってサーモンが入った袋を投げた。
「んで、今日はどうしたのよ。こっちに来るのは結構珍しいんじゃない?」
「まあ、ミロクに会いたかったからね」
「・・・」
ミロクはそっぽを向いている。
うん、ちょっと可愛い。
「ほら、懐刀にちょっとした情報共有をと思いまして」
「だから、いつアンタの懐刀になったのよ」
と、彼女は、あいも変わらず否定している。
「いやほら、こないだのヴィアラッテアの一件を解決したあたりから、街の人がそう言い始めてるの聞いたんだよね」
「ああ、あれか・・・」
そもそも彼女は、このヴェネツィアの住人ではない。
彼女曰く、遥か東にある、「ホウライサン」と言う場所からやってきている、らしい。
信仰から異なっており、彼女は仏教徒である。
私たちとは違う主を信仰しており、本人曰く、「アジャリ」というらしい。
元は、東方から西に向けて旅をしている中で、「気づいたら」庭園に入り込んでしまっており、侵入者がいると誤解した私と交戦。
戦っている中で、彼女が本当に偶然入り込んだということがわかり、その後和解し、この街に居座ることになった。
で、ここの気弱なヨハネさんを言いくるめ、今はこのアパートの4Fを根城(居候)に、主に傭兵稼業をやっている。
傭兵というのは、都市国家間を移動するときにつける、護衛のようなものである。
最近では幻獣や魔獣がそれなりに活発化してきており、特に山々を巡ったり森を抜けたりする際には、護衛が必要となることが多い。
(彼女の剣術や法術は中々のもので、その戦闘力は直に戦った私から見ても折り紙付きだ。)
なので、都市国家間を移動しようとしている人に対して彼女を紹介したりしているが、彼女は生粋のヴェネツィア住人ではないということもあり、なんだかんだ私の方からも色々と相談をしてしまうのだ。
都市の治外法権としての守護聖人と、この流浪人仏教徒との相性は思いの外良く、賢人たちの目の届かない問題を二人で対処してきた結果、彼女は守護聖人の懐刀と呼ばれるようになってしまい、最近では、治外法権が保有する個別戦力として、認識されつつある。
私個人としてはそれでも全く問題ないのだが、政治的には当然問題ありと認識されてしまっていた。
そのため、ここ最近では、目立つ接触はしないようにしていたのだ。
「だから、ミロク成分がちょっとたりてないんだよね・・・」
「・・・対して健康に良くないわよ、その成分」
と、彼女は自虐的に言った。
「で、今度は何があったの?」
「今日の午前中、トロイメライさんに会いに行ってたんだ」
「あの胡散臭い爺ね。私、あいつと喋りたくないわ」
「ちょっとお茶目な方向にぶっ飛んでるけど、基本はいい人だよ」
「どうだか。ああいう手合いは、実力がある癖に目的が見えないもんだから、誰から見ても敵か味方かわからない。結局は混乱を引き起こすだけよ。」
ミロクは意外と容赦がなかった。
「まあ、だから賢人なんてやってるんでしょうけどね。で、その胡散臭さの極みみたいな爺が、今度はなんて言ってたの?」
「トロイメライさん、賢人辞めたらしいよ」
「・・・ん゙ん゙っ?」
ミロクの喉から、なんて発音していいかわからない擬音が出てきた。
「・・・えっと、マジ?」
「うん、本当。ついでに、旅に出る、って言ってた。」
「・・・」
と、彼女は黙りこくってしまった。
まだこの街にきてそこまで日が立っていない彼女でも、トロイメライの影響力の大きさを知っている。
何せ、当代最高の占い師でもあったのだ。
街の多くの人が、彼の予言を頼りにしているのは、周知の事実であり、その彼が賢人をやめ、あまつさえ旅に出てしまえば、街は一時的にでも混乱が起きるのは間違いない。
「っていうかそもそも、トロイメライは七賢人の中でも守護聖人寄りの筆頭じゃない。」
「いや、まあ。それは別にあんまり関係ないかなぁ。聖人と賢人はお互いに権力の干渉がないわけだから、そもそも「聖人寄り」っていう表現自体が、ちょっとおかしかったんだよね。」
「まあ、アンタがそこを気にしてないのなら別にいいんだけど。しっかしまた随分きな臭さそうなことだわ。」
「確かに、トロイメライさんは、最後まで旅に出る目的をきちんと教えてはくれなかったなぁ」
「どうせヒントになるかならないかわからないような適当を嘯いていたんでしょ」
「まあ、それはそうだね、、、」
そう言って、私は彼からもらった本をミロクに見せた。
もちろん、その本の中身についても、合わせて話をした。
「ミロク、これ読める?」
「読めないわ。文字が見えもしない。」
と、目を細めながら彼女は言う。
「それにしても、世界がひっくり返る、ねぇ。」
「何を意味してるか、さっぱりなんだよねぇ」
「だーからロクなもんじゃないのよあの爺は。そもそもこれ、グリモワールって言っても、魔術書じゃなくて、魔法書でしょ?」
「まあ、そこまでは聞いてないけど、それは間違いないと思う。」
「なら、なおのこと厳重封印ね。単なるエントロピー操作の延長線上でしかない魔術と違って、魔法は神の権能と同列。何でもあり。だからこそ、まかり間違って読める人の手に渡った時には、何が起きてもおかしくない。それこそ世界がひっくり返るような天変地異でもね。」
「まあ、そうなるよね。この本に関しては、封印を施した上で、私が肌身離さず持っているようにしようと思う。」
「はぁ、まためんどくさい重しを置いていったものだわあの爺も。」
と、ため息を吐くミロク。
本を彼女が持つわけでもないのに、ため息をついてくれることに、何でか少し嬉しくなってしまった。
「何ニヤニヤしてるのよ」
「ごめん、何でもない」
「ともかく、しばらく騒がしくなることは事実じゃないの?あのトロイメライが辞めるのなら」
「そうだね、早ければ明日。遅くとも、一ヶ月後には、皆が知られることにはなってると思う」
「そしたら、しばらくはクソ忙しいでしょうね。私にとっては稼ぎどきかもしれないけど。」
「なんだかんだ、彼にみんな頼ってきたところがあるからね。この都市は」
と、そんなことを言いながら、私とミロクはしばらく、この後のヴェネツィアの動向の予想を話し込んでいた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
カフェイルジオーネの窓から、西日が店内を照らし出す。
ひとしきり店内で盛り上がっていた私たち以外に、客はいない。
そういう意味でもここは、作戦会議をするにとっておきの場所だった。
入り口の立地にやや問題があるものの、窓辺から海が見えるこのカフェを、私は気に入っていた。
窓からは、波の音と、船が往来する音が聞こえる。
そんな中、西日に消え入りそうなミロクを見て、ふと、尋ねてしまった。
「ねえ、ミロクは、この先の人生、どう生きていくか決めているの?」
「何よ、急に改まって」
と、彼女はこちらを見る。
「いやその、しばらくしたら、また西に向かう旅を始めるのかなって思って。」
と、自分でも何を聞きたいのかわからないまま、彼女に話しかける。
「うーん、今しばらくはこの街を拠点にするつもりよ。何だかんだこの街は面白いし、住む場所もあって、稼げるだけの交流もできた。」
「そっか」
と、少し安堵している自分がいる。
「何よ、そんなつっかえ棒みたいな物の喋り方して」
「あ、いや、これを貴方に話すのは、重荷になるかなと思って」
と、私はいつも、最後の一歩の距離を詰めようとしない。
「何変なこと気にしてんのよ。いいから喋ってみなさい。このミロク様が大概のことは聞いてあげるわ」
だから、次の一言を話すための勇気をくれたミロクに、最大限の感謝をしつつ。
「ミロク。私はミロクに、本当の意味で、私の懐刀になって欲しいと思ってる」
思えば、これが生まれて初めて、自分の意思で、人の人生に干渉しようとしたのかもしれなかった。
「・・・」
「この世界の発展と、表側の人類の発展は、文字通り表裏一体。
それは、ミロクも知っての通りだと思う。
そしてここ百年。急激に表側からの知識体系の流入が進んでいる。
それは、表側では、どんどんと新しい知識の発明と断絶が進んでいるということ。
つまり、これからもっと多くの知識達が、この世界に押し寄せてくるんだ。
多分、トロイメライさんが言ってた、これから起こる多くのことは、
表側からの知識体系の流入によって、
この世界に元々在った存在が活性化されて起きるんだと思う。
その流れは、これからどんどん大きく、そして複雑になっていく。
それに耐えうるだけの強度を、この都市は、この世界は、身につけないといけない。
でも、私の知る賢人達は、都市国家内部の内政にだけしか興味がない。
私もこの街の守護聖人であるが故に、ここを動くことができない。
でも、ミロクなら、そこを自由に飛び越えていける。」
目を見て、そこまで一息で話しーーー
「だから、私はあなたが欲しい。あなたが必要。」
今自分が投げかけるべき言葉を、力強く言い切った。
「・・・珍しいわね、アンタが自分から何かを人にお願いするのは」
「・・・そんなに珍しいかな?」
「珍しいわよ。アンタは依頼を受ける側で、依頼する側に立つのなんて初めて見たんだから。無駄に礼儀正しくて、虫も殺せないような性格で、それでいて芯だけ強い受け身なやつだと思ってたのに」
高いか低いかわからないような評価だなぁ、と思った。
その評価をどう受け止めるべきか、やや当惑していると。
「まあ、だからいいわよ」
と言う、不器用な友人の声が聞こえた。
「アンタの刀になってやるわよ。アリシアからの依頼なんて、中々こんな機会ないじゃない」
と、顔を赤らめて言う彼女の声が、嬉しくて頼もしくて、つい。
「ありがとう!頑張ろうね!」
と思いきり手を握ってぶんぶんと振り回してしまった。
「何よ、そんな嬉しそうにはしゃいで」
「だってそれは、ほんとに嬉しいんだし?」
「まあ、乗りかかった舟だわ。しょうがないからやってやるわよ。ついでに、どっかのタイミングで、あんたを外に連れ出してやるんだから」
「え」
と、こちらが予想してなかった条項が追加された。
「そりゃそうでしょ。私が目になったって、あんたつまんないじゃない。」
「いや、まあ、それはそうなんだけど?」
「何よ。自覚あったんじゃない。これはそうね、私からの約束にしといたげる」
夕焼けの中で、彼女はカラッとした笑顔で私にそう言った。
捻くれ者のミロクが、
そんなありきたりなセリフを言うのが、
あんまりにも不自然だったものだから。
私はまた、思わず笑い返してしまうのだった。